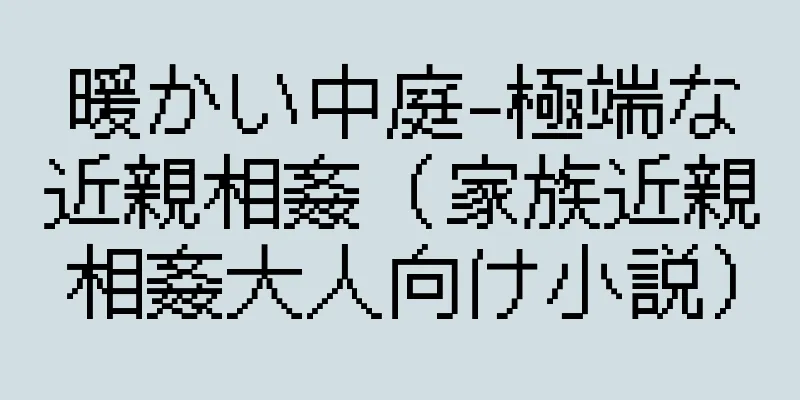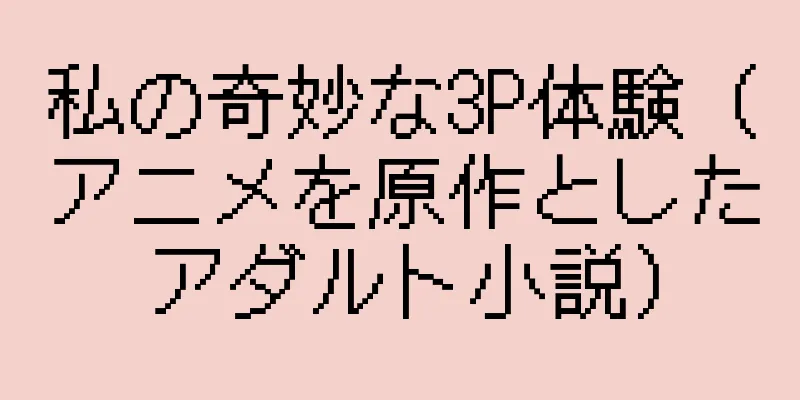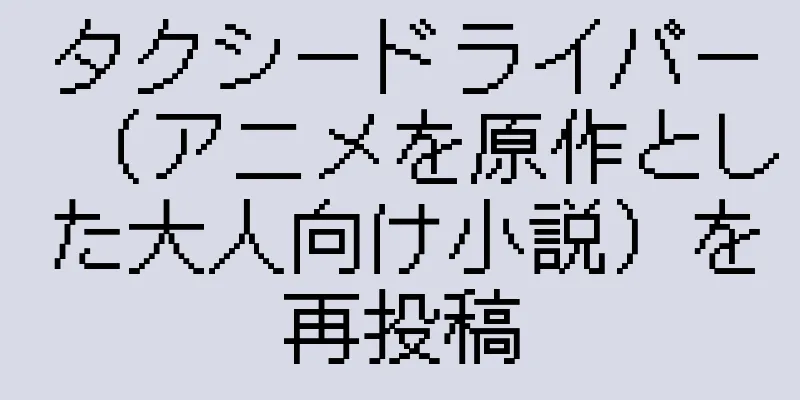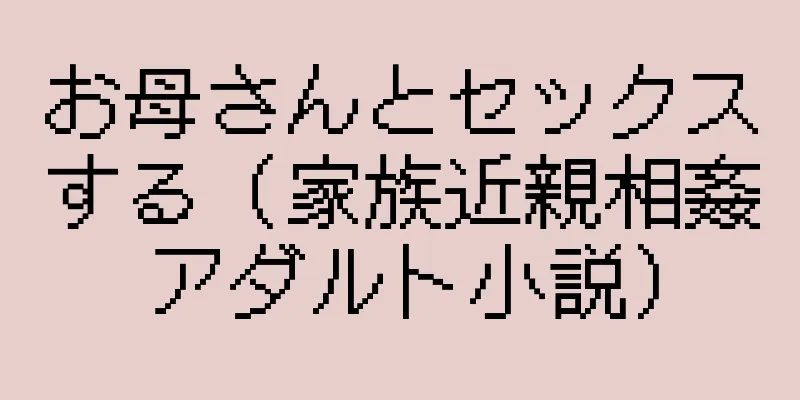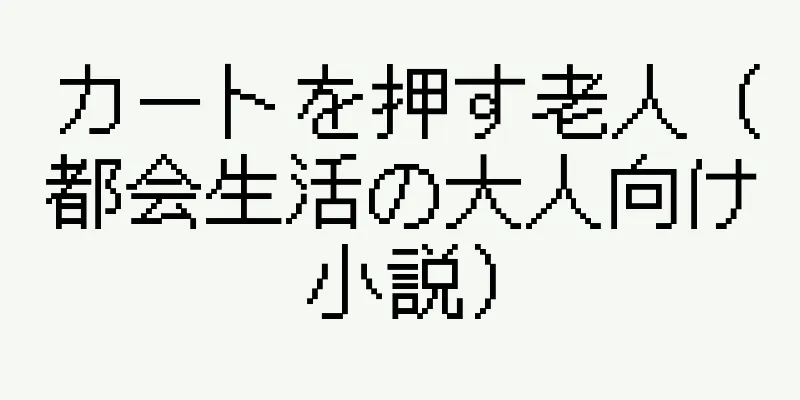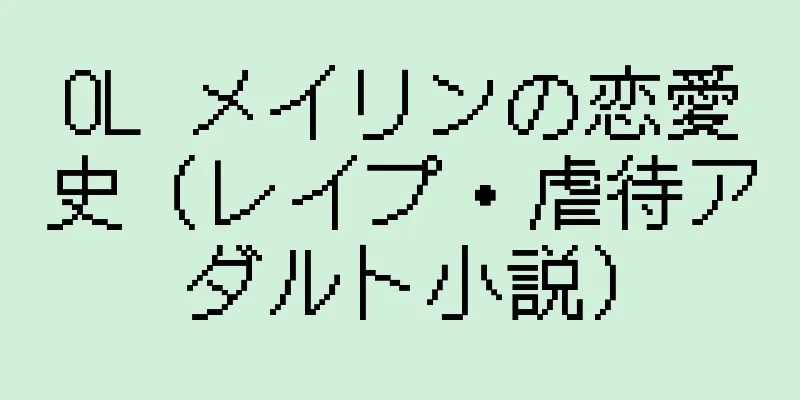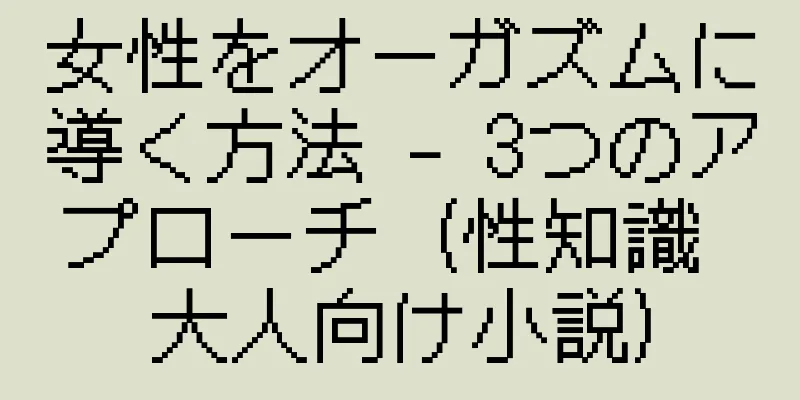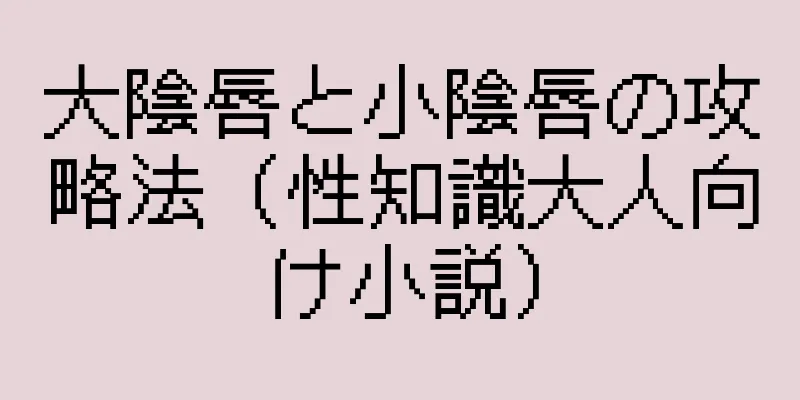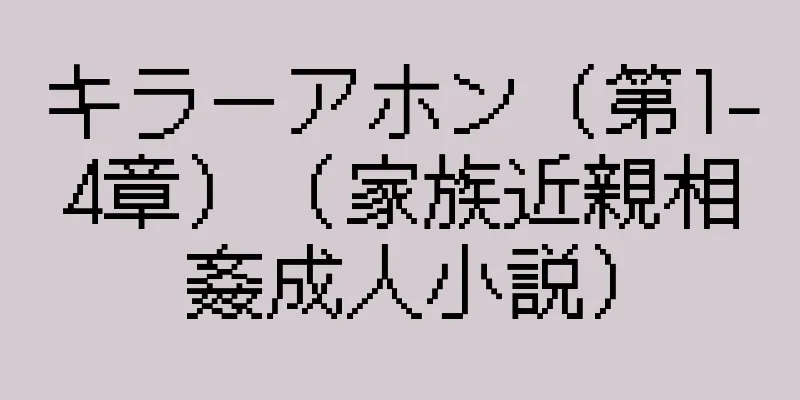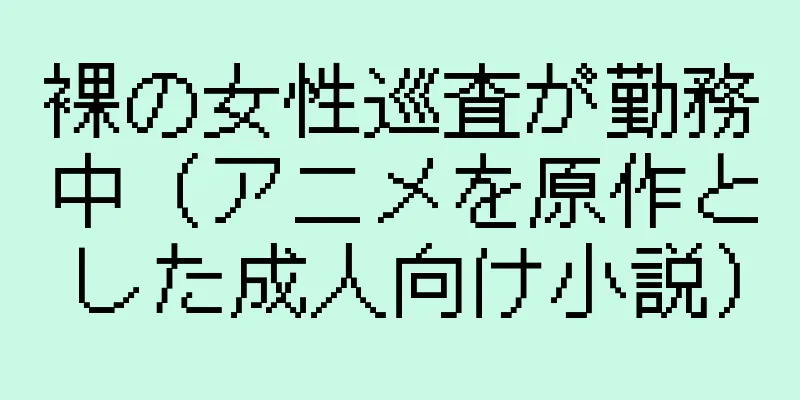悪魔と美女 7-8 (体験談 大人向け小説)
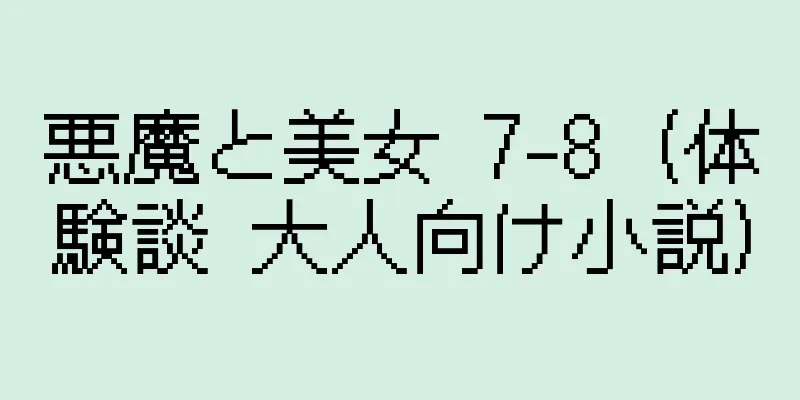
|
悪魔と美女 第7章 夜明けとともに太陽が昇り、何千もの金色の光線が皇帝の首都長安を金色に照らしました。市内の東市場と西市場はすでに営業を開始している。この場所は昔から裕福な商人たちが集まる場所であり、今でもシルクロードからこの2つの市場に商品を買い付けるために全国から商人が大勢訪れます。商人たちの間で最も人気のある品物は、象牙、沈香、真珠、錦、鼈甲鏡などです。 首都の通りは広くて清潔で、高い建物が並んでいます。しかし、周囲にそびえ立つ建物を見ると、その建築は豪華で、荘厳で、壮大で、荘厳であり、人々の心をゆっくりと打つ王室のオーラを感じさせます。 両市の西側には万年県の管轄下にある平岡坊がある。北西の角は皇城に近いです。 。唐の建国以来、多くの王子、大臣、高官、宮廷の貴族たちがここに集まり、暮らしてきました。平康坊は東市場に近く、東門の周辺は北から南まで売春婦の集まる場所となっているからです。また、王城の有名な「方曲」の所在地でもあります。このため、平康坊はさらに活気に満ちています。 このエリアにはいたるところに茶屋や酒屋があり、5歩ごとに建物や居酒屋があり、10歩ごとに居酒屋があります。夜通し騒々しい音楽と歌声が響き渡ります。地元の人々はこの場所を「ロマンスの温床」と呼んでいます。 徳静王武三思の邸宅は平岡坊の北端に位置し、その邸宅は皇宮のように豪華で、軒が高く、建物は彩色され、梁は彫刻が施され、扉や窓は金で彫られ、壁は白玉で飾られており、豪華さと浪費の傑作であった。 この時、空は金色の太陽で満たされ、昇る太陽が窓から輝いています。錦のカーテンの後ろでは、権力のある徳静王子がまだ美しい女性を腕に抱いて眠っています。この大臣は第一位の高官でありながら朝廷にも出席せず、まさに皇帝を蔑ろにしていた。甘い夢に酔いしれていると、部屋の外からナイチンゲールのような叱責の声が聞こえた。「何ですって?このお姫様も入れないなんて。死を求めているのね。」 哀れな女性の声が言った。「姫様...はい...王子様はすでに誰にも邪魔をさせないように命じておられます。本当に...」 呉三思はすぐにドアの外の騒音で目を覚ました。怒りが爆発しそうになったとき、「姫」という言葉を聞いて、到着したのは安楽姫だと気づいた。太い眉毛が思わず引き締まり、大きな声で「姫を入れなさい」と言った。言い終わる前に、誰かが部屋に入ってくるのが見えた。よく見ると、それはとても美しくて、目を見張るような容貌の少女だった。彼女は秋の水のように明るい大きな目で、ソファーに座っている二人を見つめていた。 彼女は18、9歳くらいで、細身の体型で、蝉の羽のドレスを着て、腰には鱗模様のベルトを締めていた。胸元の開いた唐時代の繻子のドレスからは、豊かで張りのある胸が半分見え、彼女の肌はより透き通って魅力的に見えた。 安楽公主は目の前にいる義父を見ると、美しい目で思わずイライラした表情を浮かべ、艶かしく言った。「まあ、あなたは一日も女なしでは何もできないわね。太陽はもう空高く昇ってあなたのお尻を照らしているのに、あなたはまだ女を抱きしめて酔って昼も夜も忘れている。宮中で何か大きなことが起こっているのを知ってるの?」 呉三思の息子呉崇勲と結婚して以来、彼女のわがままな性格は変わっていないどころか、ますますひどくなっていた。彼女にとって、母である衛皇后以外の誰に対しても、目の前にいる義父はおろか、現皇帝の父に対してさえも、真剣に受け止めることはなかった。 武三思は非常に権力を握っていたが、それでもこの手に負えない王女に対しては寛容な態度を見せていた。彼は彼女を恐れていたわけではなく、彼女を大いに活用することができた。宮殿で何か大きな出来事が起こったと彼女が言うのを聞いたとき、彼はショックを受けてすぐに立ち上がり、隣にいた裸の美女を軽くたたいて、先に出て行くように頼みました。 その美女は武三思の六番目の側室、迎雪でした。彼女は容姿が美しく、技巧も優れているため、普段は武三思に気に入られていました。しかし、目の前の美しい姫君の前では、自分の身長が三センチも低いと感じざるを得ませんでした。この時、呉三思は彼女に出て行くように言ったが、もちろん彼女は一言も言う勇気がなく、急いで服を着て部屋を出て行った。 迎雪が去った後、武三思は安楽公主に向かって「何が問題なの?」と尋ねた。 安楽公主は二、三歩で彼のところに近づき、目には涙があふれていた。「あなたはただ女遊びばかりしていて、嫁の生死など気にしていません。お父様、今朝李崇俊を皇太子に立てられたのです。」 武三思はこれを聞いて、最初はびっくりしたが、その後、竜の目のように大きな目が眼窩の中で何度か回転し、首を振って言った。「皇帝はただ話しているだけだと思っていたが、それが深刻なことだとは思わなかった。皇帝はなぜ、このような大きなことを私に知らせなかったのか!」 安楽公主はこれを聞いて思わず涙を流し、足を踏み鳴らして言った。「四番目の叔父と叔母の太平が父の耳元で、皇太子を立てることは朝廷の安定に関わる問題なので、軽視すべきではないとささやき続けていたのです。腹立たしく思いませんか?」 皇帝が皇太子を立てる問題は、ここ数日、宮廷や後宮で広く話題になっている。李崇俊は後宮の妾の子として生まれた。衛皇后はそれを聞いて、止めようとした。しかし、彼女の一人息子である李崇潤は数年前に武則天に殺され、衛皇后は言葉を失った。しかし、安楽公主は違った。彼女はずっと両親に愛され、魏皇后の嫡女だった。心の中では、兄が亡くなったのだから自分が皇太子になるべきだとずっと信じていた。女性が皇太子になれないのなら、祖母の武則天がなぜ皇太子になれるというのか? 実際、彼女の父である中宗皇帝も彼女の願いに同意したいと考え、中書大臣の魏元忠に尋ねました。「私は安楽公主を皇太子妃にしたいのですが、あなたはそうする意志がありますか?」 しかし、魏元中は首を横に振って言った。「王女が皇太子妃になるのは前例のないことです。それに、もし本当に皇太子妃になったら、太子妃は彼女を何と呼ぶべきでしょうか?これは許されないと思います。」これを聞いた中宗はただ頷いて笑った。 安楽公主はこれを聞いて激怒し、中宗皇帝の元に駆け寄り、こう罵った。「あの魏元忠とは誰だ?この愚かな大臣は何も考えていない。母と息子が皇帝なのに、なぜ孫娘が皇帝になれないのか?」 中宗は愛娘が激怒しているのを見て、ただ微笑んで「ゆっくり考えさせてください」と言った。そして彼女をなだめ、説得し、安楽公主は少し落ち着いた。 中宗には全部で8人の娘がいたが、7番目の娘である安楽公主は美しいだけでなく、非常に聡明でもあった。中宗と衛皇后の心の中では、彼女は目玉のように可愛がられ、非常に溺愛されていた。この誇り高き天国の少女と言えば、忘れられない過去の出来事がある。 武則天が存命のとき、彼女は中宗李仙を皇帝に立てた。彼女の妻の魏は魏湘といい、荊昭の万年出身であった。彼女の祖父の魏宏標は太宗李世民の治世に曹王宮の軍司令官を務めていた。彼女の父の魏玄真は当時溥州の軍人で、八位の下級官吏であった。中宗が即位した後、彼は魏玄真を四位の地方官吏である豫州知事に昇進させた。しかし、衛皇后はまだ満足せず、中宗皇帝に父を都に戻し、宮廷侍従に任命するよう求めました。世忠の地位は宰相、中書凌、冰尚書と同等である。今回は事態はそれほど順調ではなかった。宰相の裴炎は、魏玄真は何もしていないし、突然の昇進は民衆を納得させることが難しく、朝廷の威信を傷つけるだろうと考え、懸命に阻止しようとした。 しかし、王位に就いたばかりの李仙は、時代や世の中をどう判断したらよいか分からず、自分が将来有望な人物であることさえ知らなかった。衛皇后は、美人で皇太子妃になれるほどだったが、娘の頃から反抗的な性格だった。李仙と結婚した後も、周囲には男が多く、抜け目がなく気が強く、見栄を張るのが好きだった。臆病で無能な李仙に比べると、彼女は陽の弱者であり、陰の強者だった。李仙にとって、大小の事柄の決定はほとんど彼女が下していた。衛皇后は誰かが邪魔をしているのを見て激怒し、無制限の権力を持ち、瞬きもせずに人を殺していた姑の武則天のことを忘れ、夫を昼夜問わず煽り立て、「皇帝として昇進したくても他人の言うことを聞かなければならないのか」とよく言った。 ある朝、宮廷で、裴厳は依然として同意しないと主張した。李仙は聞けば聞くほど怒りが増した。臣下の前で威張らなければ、将来皇帝であり続けることはできないと考えた。そこで李仙は怒って叱りつけた。「これ以上言う必要はない。たとえ私が魏玄真に全世界を与えたとしても、あなたには口出しする権利はない。ましてやあなたはただの小臣にすぎない。」 裴炎は彼がそのような愚かなことを言うのを聞いて、彼と議論せず、振り返って皇太后の前に行き、すべてを話しました。武則天は李仙が誰であるかを知っており、彼の発言は一時的な怒りの爆発に過ぎないことも知っていた。たとえ彼が世界を手放したいと思っても、そうする能力はなかった。しかし、彼女は、これまで鼠のように臆病だった息子が皇帝になった途端に、このような言葉を発するとは予想していませんでした。彼の翼が強くなれば、将来彼をコントロールすることは困難になるでしょう。彼女はそれを軽く考えてはならない、そして皇帝を廃位することを思いつきました。 思勝元年2月初め、武則天は突然朝廷に現れ、すべての官吏を召集し、皇帝を廃位して廬陵王にすると宣告し、官吏に李仙を王位から退けるよう命じた。今度は李賢は本当に困惑し、口ごもって言った。「私はどんな罪を犯したのですか?」 武則天は彼を睨みつけ、「国を他人に譲るつもりか?これはお前の罪だ!」と言った。李仙は言葉を失った。たった2ヶ月しか王位に就いていなかったのに、王位を失うことになるとは思ってもいなかった。彼は犯罪者のように罰を待つしかなかった。 やがて、李仙と妻は君州に追放され、その後方州に移されました。途中、家族は着ている服以外には何も持っていませんでした。当時、衛皇后はすでに妊娠しており、大きなお腹を抱えて出発しました。囚人を護衛する衛兵は、あなたが過去に王様、王子、将軍、大臣であったかどうかは気にしません。貢物として支払うお金がない限り、彼らはあなたを苦しめるでしょう。 李仙は以前皇帝だったが、これらの官吏はあなたにそのことを伝えなかった。武后があえてあなたに目をつぶったので、彼らはあえてあなたと取引したのだ。しかし、困窮したこの貴族二人は、敬意を表すためにお金をどのように取り出せばいいのか分からず、その過程で本当に苦労しました。 ある日、早朝に旅に出ようとしていた時、正午に魏皇后は突然腹部の痛みを感じ、出産間近となりました。しかし、前方に村はなく、後方に要塞もありませんでした。衛皇后がひどく苦しんでいるのを見て、李仙は召使に懇願するしかありませんでした。「姫様がもうすぐ出産します。しばらく滞在してもらえますか?」 二人の警官はこれを見て顔をしかめ、怒って言った。「赤ちゃんを産んでもらいたいなら、急げ。二時間は与える。それができないなら、これ以上待てない。宿場に行けないなら、今夜どうやって食料と宿を確保すればいいんだ?」 李仙はそれを聞いてすぐにうなずいた。「もうすぐだよ、もうすぐだよ…」 二人の警官はそれ以上何も言わず、大きな木の方へ歩いていった。警官の一人が笑って言った。「赤ちゃんが産まれると言えば、産まれる。言うのは簡単だ」。予想外に、彼が言い終えるとすぐに、背後から泣き声が聞こえた。警官は顔を見合わせた。 李仙は数人の子供の父親であったが、王子である彼がどうしてそのようなことを個人的に行うことができたのだろうか? 彼はすぐに途方に暮れ、赤ん坊を見て、どうしたらよいか分からなかった。 幸いにも、魏皇后は力持ちで、へその緒を口で噛み切った。 彼女は李仙に「早く服を脱いで、赤ん坊を包みなさい」と言った。 これを聞いた李仙はすぐに服を脱いで、赤ん坊を包み、魏皇后は赤ん坊を抱き、授乳を始めた。 警官たちは、彼らが排便のように速く動いているのを見て驚いた。彼らは集まって、自分たちを守っているのは山の神なのだろうかと互いにささやき合った。そうでなければ、どうして赤ちゃんを産むのがこんなに簡単なのだろうか。ある人は「これを見ると、王子様の将来はきっと幸運に恵まれるだろう」と言いました。 別の人はこう言いました。「その通りです。喧嘩の後は相手を大事に扱うべきです。そうでないと、自分が苦しむことになりますよ。」 しばらくして、李仙は出発するように彼らに呼びかけました。召使たちは急いで駆けつけ、すぐに表情を変えて、笑顔で言いました。「殿下、ご心配なく。姫は出産したばかりですので、もっと休んでください。何か必要なことがあれば、お知らせください。」 李賢は非常に驚き、しばらく理由がわからなかったが、こう言った。「兄さんたちの祝福のおかげで、今日はすべて順調に進みました。将来良い日が来たら、必ず恩返しします。」 これを聞いた皆はひざまずいて、一斉に「ありがとうございます、殿下!」と言いました。馬車の中でこれを見た魏皇后は思わず笑ってしまいました。 警官は「王子様ですか、それとも王女様ですか?」と尋ねました。 李仙さんは「私の7番目の娘です」と言った。 男はすぐに言いました。「それで、お姫様だったんですね。よかった。名前はあるのかな?」 衛皇后は馬車の中で、「彼女に赤ちゃんを包んでもらうのはいかがですか? どう思いますか?」と言いました。 李仙は髭を撫でながら微笑んだ。「まあ、この名前はいいでしょう?」皆が同意してうなずいた。李仙は付け加えた。「古児は生まれたときから不幸を幸運に変えることができました。この娘は幸運をもたらしてくれるようです。」 案の定、この娘は美しいだけでなく、李仙が言った通り、ついに武則天に宮殿に迎え入れられ、李仙は再び帝位に就いて中宗皇帝となった。 呉三思はこれを聞くと、心の中で密かに計算し、こう考えた。「李崇俊はずっと私と対立していた。彼が権力を握った今、私の大業に支障はないが、常に隠れた心配事だ。この子がこの席に座る徳は何だろうか?私が彼を失脚させなければ、呉家の将来は明るいだろうか!」そして、安楽公主に向かって言った。「いい子だ、悲しまなくていい。皇帝はいつも混乱しているが、李崇俊が着実に席に座ることは許されないことを知っているはずだ。安心してくれ、すべては私次第だ。外廷の廷臣たちは、私の一言でどうして私に逆らうのか?王子の地位を取り戻すのは簡単だ。あなたも宮殿に戻って、母に父にもっと圧力をかけるように言いなさい。あの男を失脚させることはできないと思う。もう泣かないで、あなたの主人もとても... 私は長い間あなたを愛していませんでした。私のところに来て、今日は私の愛しい妻としてあなたを愛させてください。 ” 顧児は唇を尖らせて彼を睨みつけ、こう言った。「あなたはいつもこうなんです。私の義父は私の義父とは違うんです。彼は他人の母親を奪い、その娘まで奪ったんです。」 呉三思は淫らな笑い声をあげて言った。「私の嫁がこんなに綺麗で可愛いなんて、誰が言ったんだ?今、父も私もあなたを幸せにしているのに、あなたはまだそんな皮肉なことを言うのね。」 顧児は細い腰を揺らし、ソファの端に座りながら言った。「あなたのような大きな息子など、誰が気にするの?母と息子が私との結婚を望まないなら、私も望まないわ。」この言葉は半ば冗談だったが、呉三思は気に入らなかった。彼は眉をひそめ、顔を暗くした。郭児はそれを見て、やりすぎたと悟り、彼に微笑みかけ、曲線美の体を彼に押し付けて言った。「そんなことしないで。私が冗談を言うのが大好きなのは知ってるでしょ。でも、あなたの長男が朝早くから私を怒らせたから、今そんなことを言ってしまったのよ。」 呉三思は尋ねた。「彼はどうしたの?若いカップルは喧嘩ばかりしているだけよ!」 呉三思は手を伸ばして彼を抱きしめ、彼の奇妙な手の一つがゆっくりと彼女の体を撫で、郭児は全身がぐったりし、ゆっくりと彼の腕の中に倒れ込んだ。 顧児は小さく息を切らしながら言った。「お前は……お前は良い息子だ、私が怒っていることすら知らない。私がそのことを彼に話したとき、彼は何と言ったと思う? 彼は、女である私がどうして皇太子妃の座を争えるのかと言った。それは竹籠で水を汲むようなもので、労力の無駄だと言った。彼は憎らしいと思うか、そうでないと思うか?」 呉三思は笑って言った。「この男はただ人に冷水を浴びせるのが好きなだけだ。気にしなくていい。」それから、彼女のベルトを外し始めた。顧児は振り回すことなく、ただ自分で外した。すぐに、彼女は呉三思と同じように裸になった。 呉三思は50歳を超えているが、健康状態は良好である。蒼瓊宗に入信し、天墨を師と仰いで以来、この20年間で相当な内なる力を築き上げ、武術の修行を始める前よりもさらに精力的である。女遊びといえば、それは彼の得意技だった。家にいる妻や妾は言うまでもなく、若い妻の郭児、母の衛皇后、李仙の妾の尚官婉児、後宮の妾など、十数人が相手だった。彼が相手にしたのは、当時の有名な美女や宮廷の貴族たちばかりで、彼が望めば誰でも手に入れることができた。実際、彼の外見は、太い眉毛、高い頬骨、無精ひげで、ハンサムというよりは威厳があるが、多くの美女が彼のところに来て、彼に利用されてしまう。残念だ。武三思は宝物が多いだけでなく、性的力も強い。 彼と性交したことのある女性たちは皆、彼の記憶を何度も思い出すだろう。他人のことはさておき、この手に負えない李桂児公主でさえ、1年前に彼を味わった後、この義父が息子より何倍も強いことに気づいた。彼女の母親でさえ武三思に執着していたのも不思議ではない。 呉三思は郭児をそっとソファに座らせ、その若々しく魅力的な体と髭を生やした顔を眺め、身を乗り出して彼女の首に触れ、クリームのように柔らかい彼女の美しい顔に寄りかかった。 彼の荒いひげが彼女を傷つけると、顧児は全身を震わせ、美しい目を閉じて優しく言った。「お義父さん、奥さんは我慢できないんです。もうからかわないで、いいですか?」 呉三思は聞こえないふりをして無視し、ただ彼女を抱きしめた。彼女の頬、こめかみ、髪、そして耳に至るまで、彼女から発せられる不思議な香りを嗅ぎました。この嫁は本当に憧れの存在だ。彼の手はゆっくりと下へ動き、彼女の胸へと滑り込んだ。そして彼は彼女の心臓の鼓動が早くなっているのをはっきりと感じた。もう少し動かすと、彼の大きな手はすでに彼女の若くて豊かな胸に触れていた。 「うーん…」グエルは満足そうな声をあげ、彼の淫らなタッチに応えるために胸を反らせたが、こう言った。「あなたは私を苦しめるのが好きなだけよ。ほら、グエルはあなたが欲しいのよ。」 呉三思は心の中で密かに微笑みながら考えた。「母と娘は似る、本当だ。この小娘、もし今日私がお前を死にたいほどの悲鳴を上げさせなければ、お前は私が何をできるか分からないだろう。」彼の考えが薄れていくと、彼の唇は彼女の顎にキスを始め、ゆっくりと彼女のそびえ立つ尖端へと下がっていき、そしてブラシのように強く彼のひげで彼女の柔らかい赤い蕾をこすった。 グーエルの体はすぐに震え、その感覚は骨の奥深くまで届くほどかゆかった。彼女は頭を後ろに傾け、小さな口をパクパクと開けたり閉じたりし続けた。からかいながら、呉三思はこの美しい嫁をじっと見つめた。見れば見るほど、彼女は繊細で魅力的だと感じた。彼女の顔立ちはどこまでも美しかった。彼がこれまで見てきた多くの美しい側室の中で、このわがままな姫は尚官婉児を除いて最も美しいと言えるだろう。 この時、顧児はもはや体の動揺に耐えられなくなり、呉三思の頬を強く抱きしめ、哀れな声で懇願した。「お嬢さん、もしあなたが顧児にこんなことをし続けるなら、私は死んでしまいます。どうか早く顧児を諦めてください。」 呉三思は笑って言った。「それはそんなに簡単なことじゃない。私はまだあなたの体を味わい尽くしていない。誰があなたに朝早く私の家に来て、義父の良い夢を台無しにするように言ったの?」 郭児はもう我慢できず、怒って言った。「わかった、頼むよ。でも、二度と私と一緒にいることは考えられないよ。」 呉三思は微笑んで言った。「その通りだ。その時が来たら後悔しないように。」彼はそう言いながらゆっくりと下へ移動し、ついに彼女がすでに甘い露を垂らしている場所に到達した。彼は彼女の胸が豊かでふっくらとしていて、花のような唇が震えているのを見た。彼は興奮せずにはいられず、すぐに身を乗り出して情熱的に吸い始めた。 グーエルは彼にこのように扱われて快感でうめき声を上げていた。さらに、彼のゴツゴツしたひげが彼女の敏感な部分を引っ掻き続け、彼女はそれに耐えることができなかった。グーエルは突然めまいを感じ、花の穴がひどくかゆくなった。しかし、呉三思は意気揚々としていた。蛇のような舌が突き刺さり、動き続け、顧児は欲望を満たすことができなかった。腰と臀部は波のように激しく揺れ、喘ぎ続けた。 呉三思も彼女が欲望に圧倒されていることを知っていたので、ひざまずいて淫らな笑みを浮かべて言った。「愛しい妻よ、あなたは十分に楽しんだ。今度は私が楽しむ番だ。」 顧児は分別のある人物で、都に戻ってから、男女間の淫らな行為をたくさん見聞きし、その影響を深く受けていた。呉崇勲と結婚する前、彼女はすでに宮中で淫らな行為にふけり、非常に淫らな行為をしていた。彼女は数え切れないほどの宮廷の召使や衛兵と遊んでおり、男性を喜ばせる方法についてすでに多くの経験を積んでいた。さらに、彼女はすでに欲望に燃えており、呉三思がそう言うのを聞いて、すぐに立ち上がり、彼の強くて厚い宝物を手に取り、彼のためにそれを演奏し始めました。 呉三思は、妖精のように可愛らしく、煙草を吸い込んでいる嫁を見下ろし、興奮を抑えきれず、歌が終わる前に彼女をソファーに押し倒した。しかし、彼は、顧児がすでに足を開いて、バラ色の誘惑的な花の穴を彼の前に完全に見せて待っていたのを見て、呉三思は激しく生唾を飲み込んだ。彼はすぐに準備を整え、槍を手に取り、馬に乗り、すぐに奥の宮殿に駆け込んだ。彼は、弟が溶鉱炉に投げ込まれたように感じました。中は暖かくて湿っていて、しっかりと締め付けられていて、動く余地はありませんでした。それは本当に極度の快感で、彼はすぐに馬に拍車をかけて疾走させ、槍を握って激しく突きました。 彼の素早い攻撃の後、郭児はすでに言葉では言い表せないほど嬉しかった。百回も繰り返した後、彼女はもう耐えられなくなった。目の前の義父は確かに勇敢な将軍であり、無能な息子よりも何倍も優れていると彼女は感じた。呉三思は彼女の赤らんだ顔と星のような目がわずかに開いているのを見て、彼女をさらに魅力的で美しくした。彼女の胸の玉のような峰が彼女の動きに合わせて前後に揺れ、それは本当に美しかった。突然、彼は全身に快感を感じた。彼は郭児を殴り殺し、跡形もなくした。彼女は何度殴られたのかわからないほどだった。彼女が慈悲を乞うて初めて、彼は彼女を抑えるのをやめた。 郭児はしばらく休んでから落ち着きを取り戻し、色っぽく言った。「あなたは無謀に遊んでいて、他人の命など気にしていない。壊したら息子にどう説明するの?」 呉三思は笑って言った。「壊したのは父親だと直接言えばいいんだよ。」 顧児は怒るべきか笑うべきか分からなかった。世の中にはこんな父親もいるのだから。それで笑って言った。「私はあなたほど恥知らずではない。あなたと私の間の問題は口外してはならない。もし皇帝の手に渡れば、私は何もできないし、あなたも首を切られてしまうのではないかと心配だ。」 武三思はそれを知っていたので、彼女に思い出させる必要はなかった。しかし、彼が最も心配していたのは衛皇后だった。彼女は後宮の奥深くにいて、彼女の出入りは必然的に疑われ、特に定安公主の夫である王通嬌はいつも彼に反対していた。彼はこのことを考えるとすぐに怒り、「あなたが私に言わなくても、あなたの妹である定安公主の良い夫が私に言わないとは保証できません。私は彼の家族全員に害を与えたわけではありません。この人はただ私と口論するのが好きなだけです。心配するなら、この人のことを心配してください。」と言った。 これを聞いた郭児は眉をひそめて「本当ですか?どうして知らないのですか?」と言った。 武三思は言った。「まだ知らないことがたくさんある。王通嬌は皇后だから、私たちは家族だ。しかし、彼は姑まで裏切った。どこから情報を得たのか分からない。彼はいつも遠慮なく話し、私とあなたの母の悪口を言う。あなたの父がそれを聞いたら、私は死んでも危険はないが、あなたの母は困るだろう。気をつけた方がいい。」 郭児は「この件の真相を究明します。あなたの言う通りなら、絶対に彼を手放しません」と言った。その後、呉三思の耳元に口を近づけて、優しく言った。「あなたはまだ満足していないようですね。さあ、もう一度妻を愛しなさい」。 呉三思は笑って言った。「この小娘、まだ息ができたばかりなのに、またすぐに欲しがるなんて。」 顧児は怒って言った。「何を言っているんだ? お前のためにやっているのに、お前は私を馬鹿にしている。イキたくないなら、もうやめて、私が立ち上がって帰れるようにしてくれ。」彼女は口を尖らせて立ち上がろうとした。呉三思は彼女がいたずらをしているだけだと知っていたので、銃を上げて彼女を軽く刺した。顧児はすぐに全身が興奮し、絶え間なくうめき声を上げ始めた。 今回も呉三思は、またもや悪戯をしました。彼は彼女の丸く張りつめた胸を弄びながら、突き刺したり突いたりしました。時々、彼は彼女を振り向かせ、後ろから攻撃しました。彼はとても荒々しく、顧児はあらゆる点で彼に従っただけでなく、とても興奮していました。彼らはそれを終えて部屋を出て行くまで、この行為は1時間以上続きました。 二人がホールから出て行くと、ホールの真ん中に灰色の服を着た老人が座っているのが見えた。呉三思は急いで前に進み出て、地面に頭を下げた。「師匠がここにいらっしゃるとは知りませんでした。おもてなしが足りず申し訳ありませんでした。」男は軽くうなずき、立ち上がるように身振りで示した。 結局、この人物は他でもない悪魔でした。彼は狄冰に騙されて以来、軽率な行動を取ることはしませんでした。狄冰の言ったことは真実だとも知っていました。「火蝉骨腐れ粉」はそれほど強力な毒であり、武術界の人々がこの毒について言及するたびに、皆が恐怖に震えていました。天墨は急いで解毒剤を塗り、狄季が卓衛を連れ去るのを見守った。彼はしばらくこのようにそこに立っていましたが、顔の灼熱感は治まるどころか、さらに強くなりました。彼はショックを受け、この子供は私に解毒剤をくれなかったのではないかと思いました。彼は密かに怖くなり、地面から解毒剤を包んでいた紙を拾い上げて嗅いでみると、辛い匂いがして、変な気分になりました。彼は有名な毒の専門家ではなかったが、何十年も武術の世界に身を置いており、毒についての知識は多少あった。解毒剤のほとんどは、毒に対して毒をもって対抗するという、穏やかな性質のものだった。 解毒剤は毒と同じ性質を持ちません。 天墨は思った。「火蝉骨腐れ粉」はもともと強い力があり、毒の部分は火のように熱く感じる。この噂は武術界では古くから知られているが、彼の手に握られている解毒剤も非常に辛い。もしかしてこれは解毒剤ではなく、「火蝉骨腐れ粉」なのだろうか!そんなことを考えると、背筋が凍り、顔に冷や汗が流れた。 しかし、天墨は心配していたものの、当面はどうしようもなく、狄冀が嘘をついていないことを祈ることしかできなかった。さらに30分後、顔の熱が徐々に治まり、以前ほど熱くなくなったことに気づいた。彼はほっとした。顔の熱が完全に治まったのは、2時間後のことだった。しかし、悪魔は毒がまだ消えていないことを恐れて、まだ動く勇気がありませんでした。一歩も踏み出せないまま、半時間以上そこに留まりました。 天墨の毒は消えたが、心の中の怒りは抑えられなかった。天墨は自分が受けた屈辱を取り戻すことを誓い、心の底から狄冀を憎んだ。実は、狄吉は昔から清廉潔白な人物で、決して他人に毒を盛ったことはなかったことも知った。彼が悪魔に使ったいわゆる毒は、ただの唐辛子粉で、解毒剤も当然同じものだった。敵を混乱させるこのような恐ろしい技は、武術の世界に長くいる人たちがよく使いますが、人によって使い方が異なり、現実のようでもあり非現実のようでもあり、なかなか理解しにくいものです。また、自己防衛のための奇襲兵器とも言えます。 ウー・サンシはまた、彼の主人が突然チャンモに来たことを知っていました。 Tianmoは何も言わなかったが、Wu Sansiの横にあるGuo'erを見て、彼女が言ったことを理解しました。 Tian Moの目は、最近皇帝のお気に入りの娘について聞いたことがありましたが、彼はすぐに立ち上がって、「私は彼女の王室の殿下に敬意を払っていると言いました。 グーアーは微笑んで言った、「マスター、そんなに礼儀正しくする必要はありません。この王女はあなたの偉大な名前も聞いています。今日は首都に来たので、急いで戻る必要はありません。 この子供は若かったが、非常に雄弁に話したのを見て、ティアン・モーは「あなたの親切に感謝します、プリンセス。実際、私はサンシと話し合うことができるので、今回はチャンアンに来ました。 ウー・サンシは喜んで言った:「それはさらに良い。マスターが留まることをいとわないことはまれだ。これは本当に私を大喜びさせます。」 彼が話し終わった後、彼は彼のそばに立っている召使に言った:「急いでマスターの部屋を準備し、キッチンに宴会をセットアップする。ウー・サンシはグオアーに目を向けて、「マスターが来るのは珍しい機会だ。プリンセスは私の家に滞在してeast宴に参加するのはどうですか?」と言いました。 グオールは彼の合意を示すためにうなずき、微笑んだ。 宴会の間、ティアン・ミズはウー・サンシに言った:「今回は格闘技の世界に戻っています。20年前から個人的な問題を解決することに加えて、私はあなたに何かを伝えることもあります。この問題はあなたと多くの関係があります。」 ウー・サンシは眉を上げて、「マスター、私の弟子と関係があるこの問題は一体何なのか?」と尋ねました。 悪魔はゆっくりと言いました、「最近、あなたは宮殿で恥ずかしがり屋で、ar慢であり、国を危険にさらしているという噂が広まりました。また、私は裁判所の誰かがあなたを排除するために格闘技のマスターを賄beした信頼できる情報を受け取りました。 これを聞いた後、ウー・サンシは少しun然としていましたが、それほど驚かなかった。しかし、Guo'erはそれを聞いたとき、彼女の顔はすぐに彼女に関連していました。 現時点では、彼の主人は、この問題のために他の理由があるに違いないと考えていました。 Tianmoは、この弟子を受け入れる際に正しい決断をしたと考えて、「さて、私は茂みの周りをbeatりません。 Tze River Basinは、過去2年間で、川の両側に広がり、しばしばこのように続くなら、それは格闘技の世界の生計に影響を与えるだけでなく、地元政府でさえもアカウントを購入する必要があります! ウー・サンシは、「マスター、どういう意味か...あなたは影のギャングと競争したいですか?」と言いました。 Tianmoはうなずき、「そうです。特に弟子を募集するために、さまざまな州や郡の空の門を追加する予定です。これは私が最も望んでいる場所ですこのように、私たちはお互いに利益をもたらすことができるだけでなく、将来の公式にも大きな助けになるでしょう。」 ウー・サンシは、それが理にかなっていると感じました。 |
推薦する
家族全員がモデルです(完全版)(家族近親相姦アダルト小説)
導入これはあまり知られていない乱交家族です。私と父と叔父を除いて、家族は全員女性です。彼女たちは普通...
ジムの美しい女性トレーナー(セレブ大人小説)
皆さんのサポートが私のモチベーションです。感謝の気持ちを表すために、右上の❤をクリックしていただけれ...
義母シリーズ 2 と 3 のセックス (家族近親相姦大人向け小説)
義母シリーズ2~3セックス私は30歳で、2人の女性と暮らしています。娘の小秋は27歳、母親の万芬は5...
絵を学ぶ私の彼女(アーバンライフ大人向け小説)
私と彼女は大学で出会いました。彼女は絵画を専攻していました。しかし、彼女に会った多くの人は、彼女が絵...
不正行為の喜び(学生向けキャンパス大人向けフィクション)
不正行為の喜び趙康は香港で一人暮らしをしているが、女性との肉欲の楽しみに欠けたことはない。彼は女性を...
美しい同級生(格闘技SF大人向け小説)
孫慧は私の大学の同級生です。卒業後は連絡が取れなくなりました。連絡を取ったとき、彼女はすでに10年近...
女上司がオナニーしているのを見てしまった(その他アダルト小説)
私は女性上司が自慰行為をしているのを見ました私は貿易会社に勤める28歳の若者です。私はここで約半年働...
747 の尼僧 (レイプとサディズムの大人向けフィクション)
747の痴女アメリカの親戚を訪ねて帰ってきたとき、私はエコノミークラスの最後尾の席に一人で座っていま...
現代の白骨悪魔(妻と成熟した大人の小説)
曹大斌さん(男性、23歳)は、1年前に広東省の中山大学を優秀な成績で卒業した。彼は現状に満足せず、家...
美しい母王燕の物語(01〜07)(セレブアダルト小説)
美しい母王燕の物語(1) 「ヤンヤン、今何時なの、どうしてまだ起きないの!早くしなさい!起きないと遅...
二人の姉妹の強盗(第2部)(格闘技SF大人向け小説)
第4章: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :...
美女図鑑 第7巻 第4章(その他の成人向け小説)
第4章 正午に畑を耕すその生き物の群れは、指ほどの大きさの翼をつけた美しい少女のようでした。背中の翼...
17のキステクニック - 欲情したあなたへ - A_A (性知識大人の小説)
17のキスの動き〜欲情したあなたへ〜A_Aルーレットの遊び方17選~塩対応のあなたへ~A_Aキスの1...
キャンプ スワップ (その他の大人向けフィクション)
アリは私のガールフレンドの古い同僚です。彼らは同じ建設会社で会計士として働いていました。二人とも同期...
欲望列車(世清編)1-5(レイプと虐待の成人向けフィクション)
第1章 プラットフォーム上の混雑した群衆を見て、Shi Qing は少し眉をひそめた。毎日9時から5...